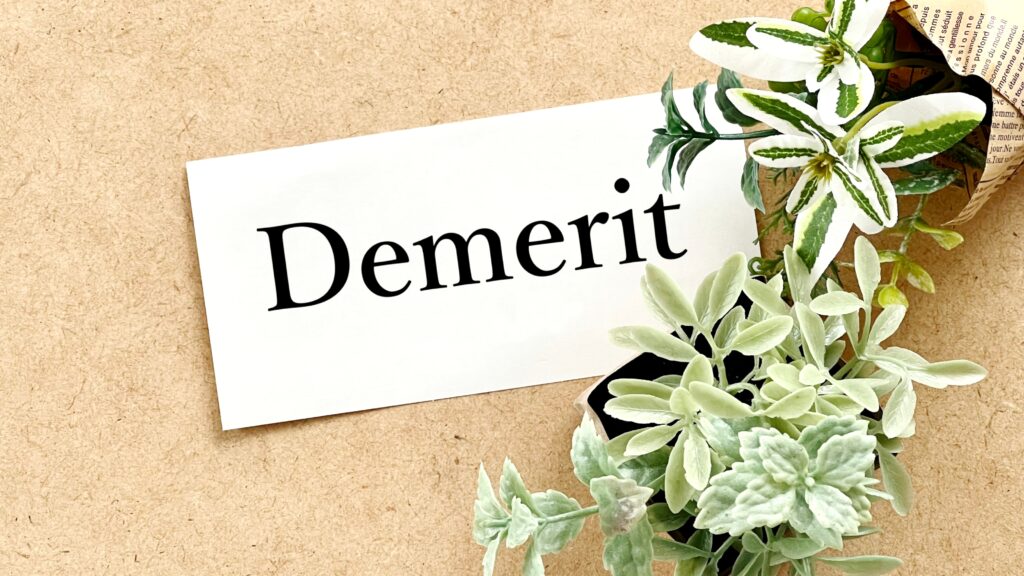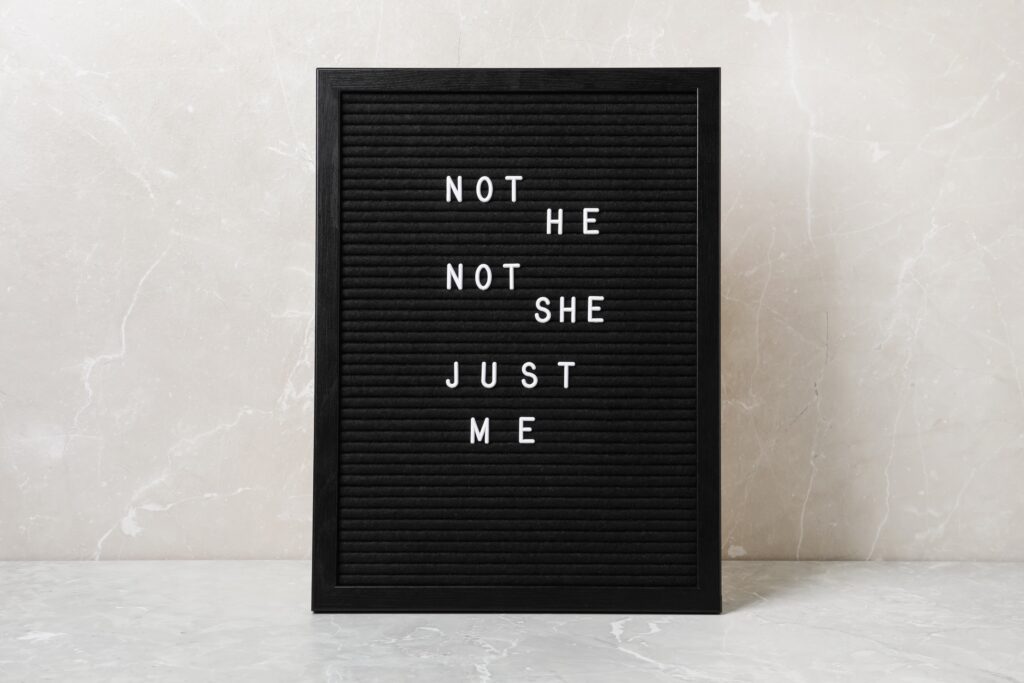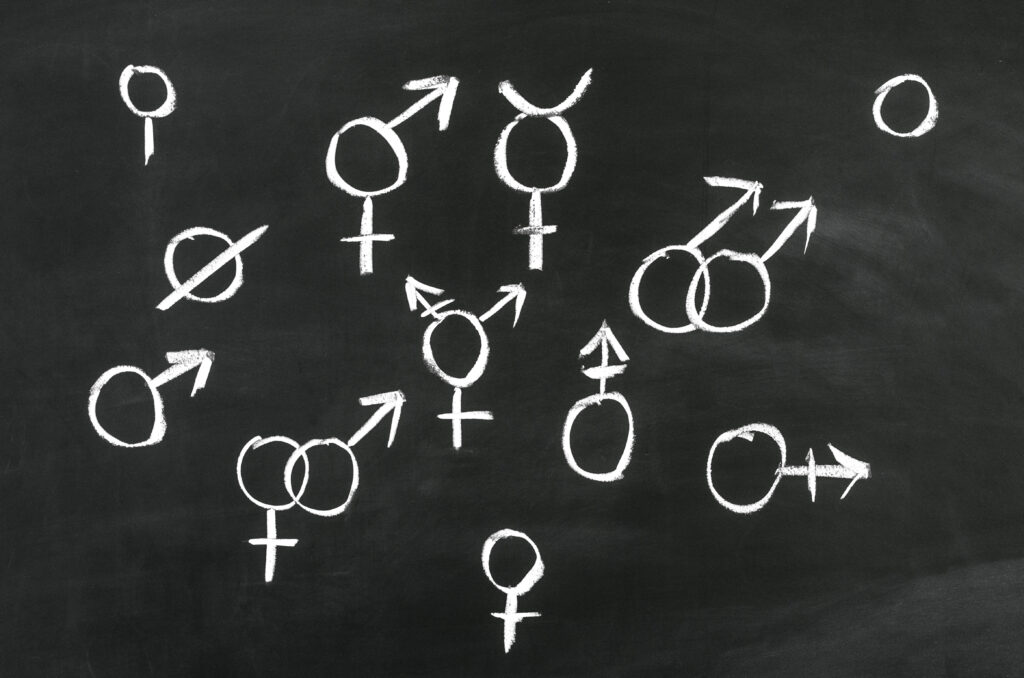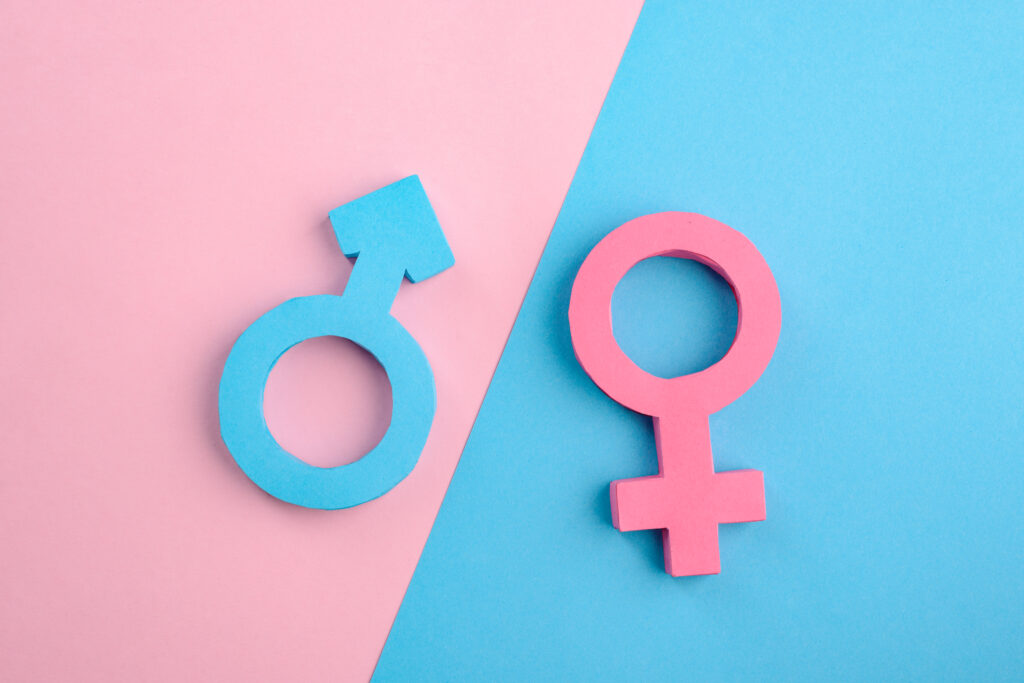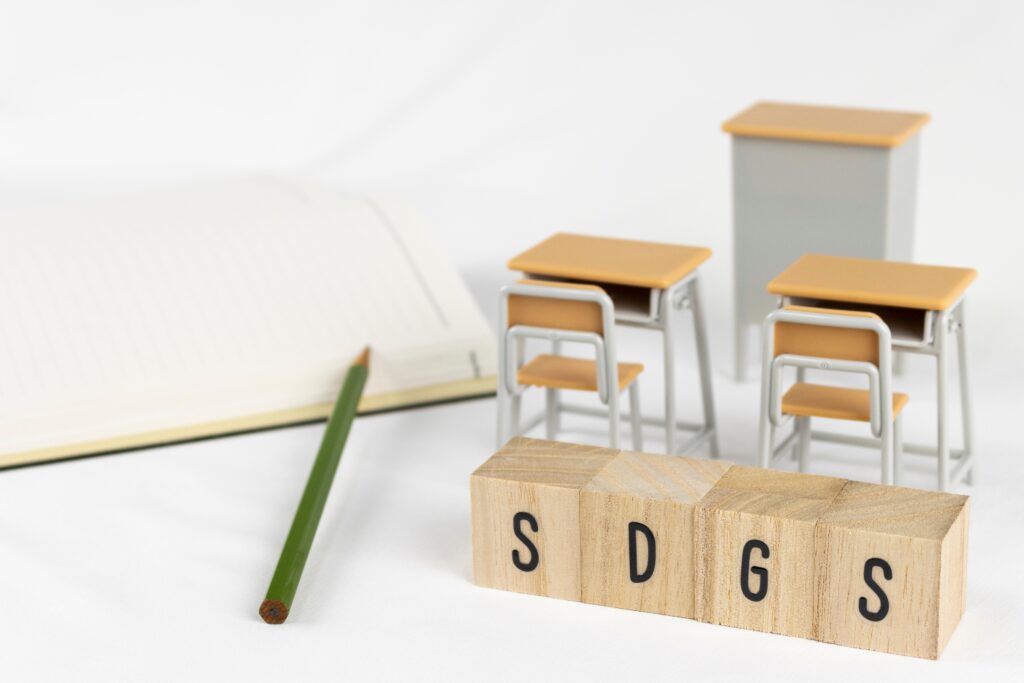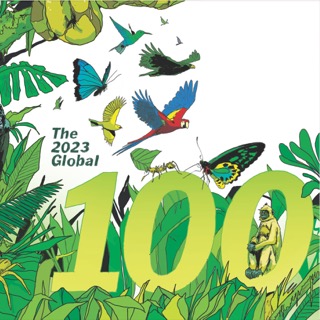国際的にジェンダーの問題や、環境の問題が注目をされています。
その中でも、日本が直面している問題の一つが女性の社会進出です。
女性の活躍は、世界中で期待がされており、経済に大きな影響をもたらすと言われています。
それでは、この課題に対して、日本ではどのような取り組みが行われているのでしょうか?
過去の歴史から現在の経済が抱える女性の社会進出に関する問題を見ていきましょう。
女性の社会進出の歴史とは?
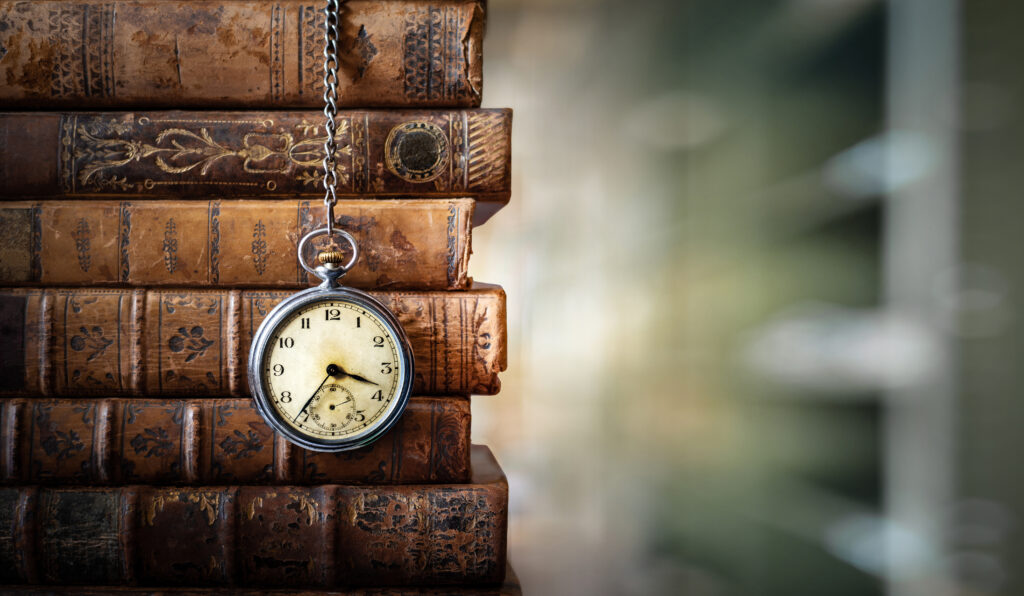
日本女性の社会進出はどのように進展してきたのでしょうか?
実は、男女平等を唱えるようになったきっかけは戦後までさかのぼるのです。
その時代は、男女の権利平等への動きが活発になり、多くの人が声をあげました。
日本だけではなく、世界の歴史も合わせて知ることで、より深く日本女性の社会進出の流れがわかります!
女性の社会進出はいつから?
日本国内で女性の社会進出が具体的に進んだのは、太平洋戦争後だと言われています。
きっかけとなったのは、アメリカが日本の法整備に参入し、男性を上位とする「家制度」が撤廃されたことです。
そして、男女平等を支持する民主主義国家へ歩みを始めたことも大きな要因の1つです。
1945年には女性が参政権を取得し、教育面でも男女共学の導入が行われました!
一気に女性の地位が男性に近づいていることがわかりますね!
世界と日本の女性社会進出
そして、世界で大きな変革のきっかけとなったのは、1975年に国際連合によって開催された「国際婦人年会議」です。
この各国の政府代表が集まった会議において、「女性の平等と発展と平和への貢献に関するメキシコ宣言」が発表され、更に、国際婦人年の目標達成のための世界行動計画が採択されました。
この国際的な動きは、日本にも大きな影響を与えました。
男女平等を実現するために、教育、雇用、育児、家庭、老後など、11の重点項目がまとめられ、具体的な取り組みが始まりました。
その結果、1985年に「男女雇用機会均等法」が制定されたのです。
「男女雇用機会均等法」は募集・採用から勤務環境はもちろん、定年・退職まで、労働に関する男女平等を網羅する法律として位置付けられました。
戦前の日本では想像がつかなかったような環境が、世界各国と足並みを揃えるようにして、一気に変化していったことがわかりますね!
女性社会進出のメリットと影響

ところで、女性が社会進出をすることでどのようなメリットと影響があるのでしょうか?
もちろん、一人一人の女性が社会的地位を得やすくなることで一個人のメリットがあるのは想像がつきますが、それと同時に日本経済全体にもたらすメリットも大きいと考えられています。
それでは、具体的に社会経済に与えるメリットと影響を見ていきましょう。
①経済成長の促進
実は、現代の日本、そして他の先進国でも、経済成長率が減少傾向にあることが問題視されています。
その原因とされる要因はこの3つ。
・少子高齢化
・需要不足、貯蓄増加(=デフレ)
・産業のIT化、技術革新の停滞
この経済成長を停滞させる3つの要因は「人材不足」という共通の問題から生まれます。そこで、期待されるのが女性の社会進出というわけなんです!
家庭の環境や、労働条件によって「働きたいけど働けない!」という女性が多く存在します。しかし、もしそのような女性たちが働くことができるように社会的な環境を整え、法整備をすれば、一気に人材不足の解消が可能となるのです。
②企業の生産性アップ
長らく日本社会では、出産や育児により退職する可能性が高い女性を雇用することは、企業にとってデメリットであると考えられてきました。
しかし近年では、その考え方に変化がでてきました。
経済産業省のデータによると、女性が社内で活躍することを推進している企業の方が、そうでない企業よりも高い利益率をあげていることがわかっています。
以前は、敬遠されがちだった女性の雇用ですが、なぜ利益率アップの理由となっているのでしょうか?
それは、女性にとって働きやすい環境を整えることによって、従業員全体の労働環境の改善が見込まれるからです。
女性が働きやすい職場環境をもつ企業は、男女間の勤続年数の差が小さく、また、再雇用制度があるため、結果として女性管理職比率が高くなります。女性管理職が増えることで、その下で働く女性は更に働きやすくなります。
このような好循環が社員一人一人に広がっていくことで、社内全体のワークライフバランスが整い、生産性アップにも繋がるんですね!
引用元:経済産業省
https://www.meti.go.jp/intro/data/hishyoka20150130.html
SDGsと女性の活躍

女性の活躍を推進することは、経済に良い影響を与える可能性があることがわかりました。しかし、まだまだ課題は多く残されています。そのため、SDGsでも女性の社会進出に関する目標が掲げられています。
SDGsと女性の活躍推進
女性の社会進出とSDGsはとても密接な関係にあります。
SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」では、働く人の権利や労働環境に関して言及がされており、その中には女性の経済への進出も含まれています。
特に目標8を細分化した項目では、女性の社会進出に密接した内容が言及されています。
8-1:各国の状況に応じて一人当たり経済成長率を持続させる。
8-5:2030年までに若者や障がい者を含むすべての男性および女性の完全かつ生産的な雇用および人間らしい雇用ならびに同一労働同一賃金を達成する。
引用元:一般社団法人 日本SDGs協会
https://japansdgs.net/target08/
まとめ

過去を振り返ると、現代まで世界で男女平等の課題に積極的に取り組んできていることがわかりましたね!
ただ、更なる発展が必要な課題でもあります。SDGsでも男女平等の取り組みがあり、今後の各国の活動に期待したいですね。
女性の社会進出が進めば、個人、企業、経済に好循環をもたらすことができます。
私たち一人一人が女性の活躍を応援することで、好循環の輪が社会全体に広がる様に取り組んでいきたいですね。