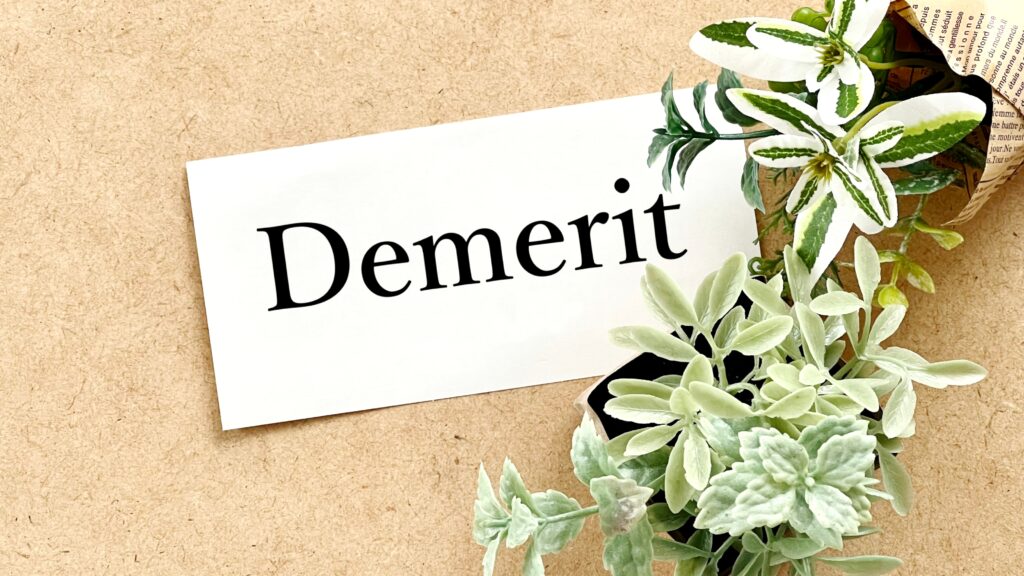今世界規模で、プラスチックゴミを減らそうとする動きがあります。
なかでも、特にプラスチックストローは環境や動物たちにとって悪影響なため、それに代わる植物由来のストローが注目を集めています!
今回は、環境に優しいと言われる植物由来のストローとは?誕生した理由やメリット、種類について詳しくご紹介したいと思います。
植物由来のストローとは?

まずは、植物由来のストローとは何なのか、誕生した理由についてをご紹介しましょう!
植物由来のストローとは、植物を使用して作ったストローのことです。
一昔前は、ストローと言えば、プラスチックのものが大部分をしめていました。
しかし、環境汚染による地球温暖化や生物絶滅の危機などが問題となってきてから、プラスチック製品の在り方が問われるようになりました。
プラスチックは、廃棄の際に燃やすことでco2が排出され、地球温暖化の原因の1つになっています。
そのため、世界中の多くの場所でプラスチックゴミを減量させる工夫が行われているのです。
プラスチックゴミの中でも、厄介なのがプラスチックストローの存在です。
プラスチックストローは、その他のプラスチック製品と比較してリサイクルしにくい性質があります。
それは細長く軽い形状が原因です。
その形状が故に、リサイクル機器の間に挟まりやすく処理が難しい、また、リサイクル回収を行った際に、すり抜けて落ちやすいなどが考えられます。
リサイクルできなかったプラスチックストローは海洋ゴミになり、鋭利さが原因で海の動物たちを傷つけてしまうのです。
2015年に公開されたウミガメの鼻にプラスチックストローが刺さっている映像は多くの人の印象に残りました。
人間にとっては便利なプラスチックストローが、海の動物にとっては危険な凶器であることがわかったのです。
そこで、プラスチックストローに代わる製品として誕生したのが、植物由来のストローです。
植物由来だけでなく、紙ストローなどのプラスチックじゃない商品も多く開発されています。
おそらく、今後はプラスチックストローの供給は減り、植物由来や紙製品のストローがメジャーとなるでしょう。
植物由来のストローのメリットは?

さて、そんな環境汚染解決のため、誕生した植物由来のストロー。
メリットはどんなところにあるのでしょうか?
1つ目は、前述した通り、環境に優しいことです。
植物由来のストローは使用後に燃やしたとしても、co2の排出量が少なくて済みます。
さらに、自然に還るものが多く、土に埋めることで堆肥となり、姿を消します。
もしも海に流れていったとしても、海中で分解され、動物たちの凶器とはなりません。
2つ目のメリットは、紙ストローよりも使用感が良いことです。
最近、飲食店ではプラスチックストローから紙ストローに代える動きが多く見られます。
紙ストローも環境に優しい部分が多いのですが、一方で「使用感が悪い」という声が多くあがっています。
その理由は、飲み物によって紙がふやけることで、飲み物本来の味を損なわせてしまうからです。
一方、植物由来のストローはふやけにくく、口に触れても違和感を感じにくいという面で、紙ストローよりも使用感が良いと口コミが拡がっています。
環境に優しいとはいえ、せっかく飲み物を飲むのですから、味を損なわないに越したことはありません。
植物由来のストローは、その両面に対応できているメリットの多いストローなのです。
植物由来のストローはどんな種類がある?

では、植物由来のストローには、どんな種類のものがあるのでしょうか?
ここでいくつかご紹介していきます。
① 草でできたストロー

1つ目は、草でできたストローです。
草の茎を利用したストローで、藁でできたストローとも呼ばれます。
ストローは英語で藁という意味なので、草でできたストローは原点に戻ったような商品と言えますね。
最近では、東京農業大学の学生たちが作った草でできたストローが話題になりました。
使い心地はまるでプラスチックストロー、でも完全自然由来で自然に還る性質を持っています。
見た目は植物の茎そのものなので、和風なドリンクにぴったりかもしれません!
② サトウキビでできたストロー

2つ目は、サトウキビでできたストローです。
サトウキビを使って作られたストローで、こちらも100%植物由来で製造でき、廃棄する際は、土に還る性質があります。
サトウキビなので、甘いストローなのでは?と想像してしまいますが、実際は無味無臭、飲む感覚はプラスチックストローに近く、耐久性にも優れています。
ただ、ギュッと潰すとパチンと割れてしまうため、ストローを噛む癖のある人は要注意かもしれません。
③ 竹でできたストロー

3つ目は、竹でできたストローです。
通常のストローサイズの細い竹を使用して作ります。
竹でできたストローには、使い捨てのものから繰り返し使えるものまで存在します。
竹には、抗菌作用があるため、清潔さを保ったまま使うことができるのは嬉しいですね。
もちろん自然由来ですし、自然に還る性質があり、さらに繰り返し使えるとなれば、一石何鳥にもなります!
④ 木でできたストロー
4つ目は、木でできたストローです。
木造住宅会社であるアキュラホームが世界で初めて開発し、話題を集めました。
日本の伝統と言われる「かんな削り」によって木を薄くスライスし、それを丸めるなどして作られている個性豊かなストローです。
こちらも、4〜5回ほど繰り返し使うことが可能で、飲み物に長時間つけてもふやけることがありません。
木の香りはなく無臭で、木製である温かみだけを感じることができます!
⑤ 米でできたストロー
5つ目は、米でできたストローです。
日本人にとって親しみやすいお米で作られたストローです。
当社の商品「RICE STRAW」もお米を使用し製造したストローで、100%天然由来の原料でできているため、土に埋めると自然に分解されます。
RICE STRAWが分解された土は栄養たっぷりの堆肥となるため、その堆肥を使用して新たな作物を育てることも可能!リサイクルよりもエコな「サーキュラーエコノミー」を実現できるストローです。
主原料には、捨てられてしまうはずだったお米=廃棄米を使用しているため、フードロス問題の改善にも貢献をしています。
使い心地もプラスチックストローに近く、飲み物の味を邪魔しないばかりか、カラフルで見た目にもこだわりを持っています。
もちろん着色料はお野菜や植物から抽出した天然着色料のみを使用しているため、全てにおいて安心して使っていただけますよ!
飲み物の種類によって、色を使い分けることができるのはその他の植物由来ストローには少ないため、飲み物やその見せ方にこだわりのあるカフェなどにおすすめですね。
まとめ
今回は、環境に優しいと言われる植物由来のストローとは?誕生した理由やメリット、種類についてご紹介しました。
植物由来のストローが誕生した理由は、プラスチックストローの環境汚染が深刻化したためです。
植物由来のストローは、環境に優しいという大きなメリットの他に、紙ストローよりも使用感が良い部分という部分があります。
種類は、「草」「サトウキビ」「竹」「木」「米」など多くのものが開発されています。
地球のこと、未来のことを考え、植物由来ストローのような環境に優しい製品を積極的に使っていきましょう!