

ジェンダーレスやジェンダーレストイレ、そしてジェンダーバイアスなどさまざまなジェンダー(=性別)に関わる言葉が注目されています。
似た言葉ではありますが、ジェンダーバイアスとジェンダーレスは全く正反対の意味になります。
それでは、今後さらに加速すると思われるジェンダーに関する知識を身につけていきましょう!
ジェンダーバイアスとは
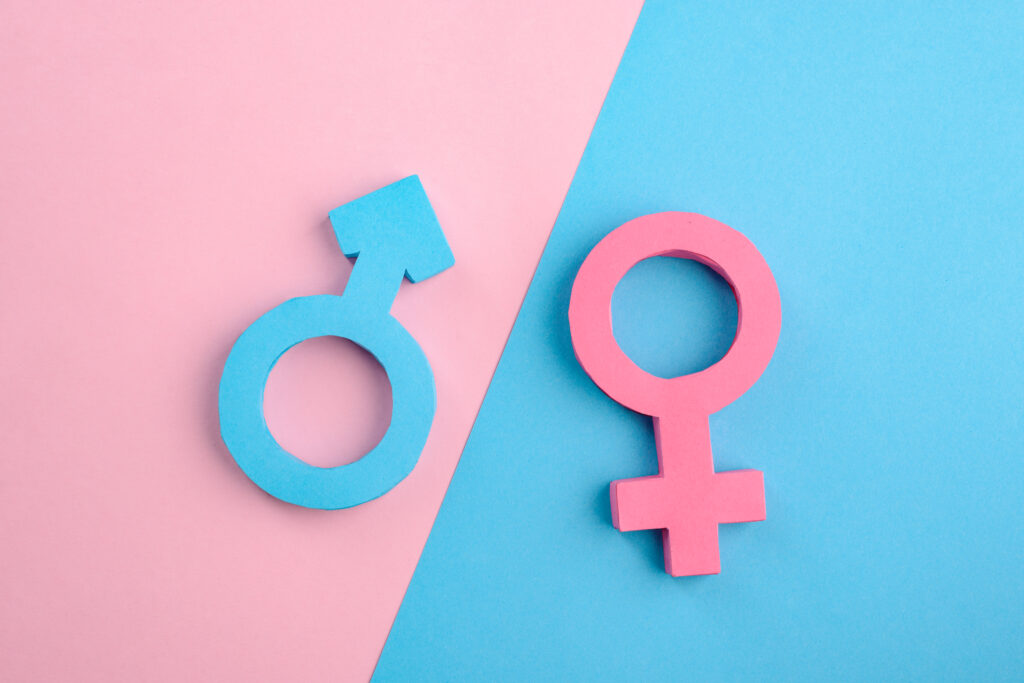
ジェンダーバイアスとは具体的にどのような意味なのでしょうか?
また、日本は現在どのようなジェンダーバイアスに関する課題を抱えているのでしょうか?
ジェンダーバイアスとは:基本的な意味と使用される場面
ジェンダーバイアスとは、ジェンダーの「性」とバイアスの「偏見」を合わせた言葉です。男性的・女性的といったジェンダーを基に社会的・家庭的地位や役割を固定的に捉えることを意味しています。
ジェンダーバイアスは、気づかない内に私たちの日常に溶け込んでいることがあります。
ジェンダーバイアスにともなう日本の現状
日本は、2023年に発表されたジェンダーギャップ指数において、日本はなんと125位…。
G7の国々の中では最下位という悲しい結果でした…。
なぜ日本のランキングはこんなにも低かったのでしょう?
それは、ジェンダーバイアスの問題において、政治参画がとても重要視されているからです。
世界で最もジェンダーレスが進んでいるアイスランドでは女性議員の割合が約50%であるのに対して、日本では約10%。その差は歴然です。
また、日本企業の管理職に着任している人の割合も男性が圧倒的に多いことが課題とされています。
※ジェンダーギャップ指数;世界経済フォーラム(WEF)が発表している男女格差を表す指数
引用元;世界経済フォーラム(World Economic Forum)
https://jp.weforum.org/
身近なジェンダーバイアスの例

それでは、ジェンダーバイアスは日常のどのような部分に現れているのでしょうか?
学校や会社はもちろんですが、家庭内にもジェンダーバイアスの事例があります。
意外と当たり前のように受け入れていた感覚がジェンダーバイアス的な考え方だったということに驚かれる方も多いかと思います。
それでは、シーン別に見ていきましょう!
学校や教育の現場に見られるジェンダーバイアス
教育現場では、文系=女性の得意分野、理系=男性の得意分野といった風に性別によって得手不得手を決める先入観が挙げられます。
昨今では、理系が得意な女性を「リケジョ」と呼ぶ風潮もありますが、このような言葉が生まれる背景にもジェンダーバイアスの影響があると言えます。
また、日本でよく見られる、体育や課外活動などの際に男女別で活動を進めたりすることもジェンダーバイアスの1つに挙げられます。
家庭や育児におけるジェンダーバイアス
育児において挙げられる例が、物の形や色のジェンダーバイアスです。
男の子が青色、女の子はピンク色というようなジェンダーによる代表的な色のイメージもジェンダーバイアスなのです。
色の問題は、トイレのマークでも顕著に現れています。
男性が青色のマーク、女性が赤色のマークで表現されているのは誰でも見たことがあると思います。
また、育児においても、女性が率先して行うものであるという考え方や、育児をする男性を「イクメン」と表現することも同様にジェンダーバイアスの一種です。
職場でのジェンダーバイアス
日本で最も問題視されていることは、政治組織に選出されている女性が少ないことです。
これは、政治や会社は男性が率先するものであるというイメージが長い歴史の中で定着したことが原因だと考えられます。
また、男性は営業職、女性は事務職を行うイメージや、女性は気配りが上手なためサービス業、男性は体力があるため建設業が得意であるというイメージもジェンダーバイアスの一例です。
ジェンダーバイアスの解消と取り組み

ここまで日常に溶け込んでいるジェンダーバイアスをご紹介してきましたが、
世界ではこの問題を改善するため、どのような取り組みをしているのでしょうか?
世界の事例とともに取り組みをご紹介します!
世界の先進例:アイスランドのジェンダーバイアス解消への取り組み
アイスランドで積極的に取り組まれているのは、育児に対する環境整備とジェンダーによる賃金格差の解消です。
性別に関係なく育児に育児に積極的に取り組むことができる環境を整えているアイスランドに対し、日本では、女性が育児休暇を取得し、男性は継続して働くという風潮が昔からあります。
その結果、日本の育児休暇取得率は10%未満であるのに対し、アイスランドでは70%以上と言われています。
また、アイスランドでは、1961年に「男女同等賃金法」が定められています。
さらに、政府組織の中に「ジェンダー平等センター」、「ジェンダー平等理事会」、「ジェンダー平等苦情委員会」といった組織が独立して設立されています。
そのため、ジェンダーバイアスの考え方を踏まえた法整備も行うことができ、男女の賃金格差解消への具体策になっています。
まとめ

ジェンダーバイアスの怖いところは、私たちが気づかない内に日常生活に自然に入り込んでいること、またイメージとして植え付けられてしまっていることです。
歴史や文化により、無意識のうちに私たちの考え方に溶け込んでしまっているのが怖いところ。
そんな特徴故に、ジェンダーバイアス問題をすぐに解決することは難しいかもしれません。
しかし、ジェンダーバイアスを日常から意識することで、あなたの日常の見え方が変わるでしょう!


