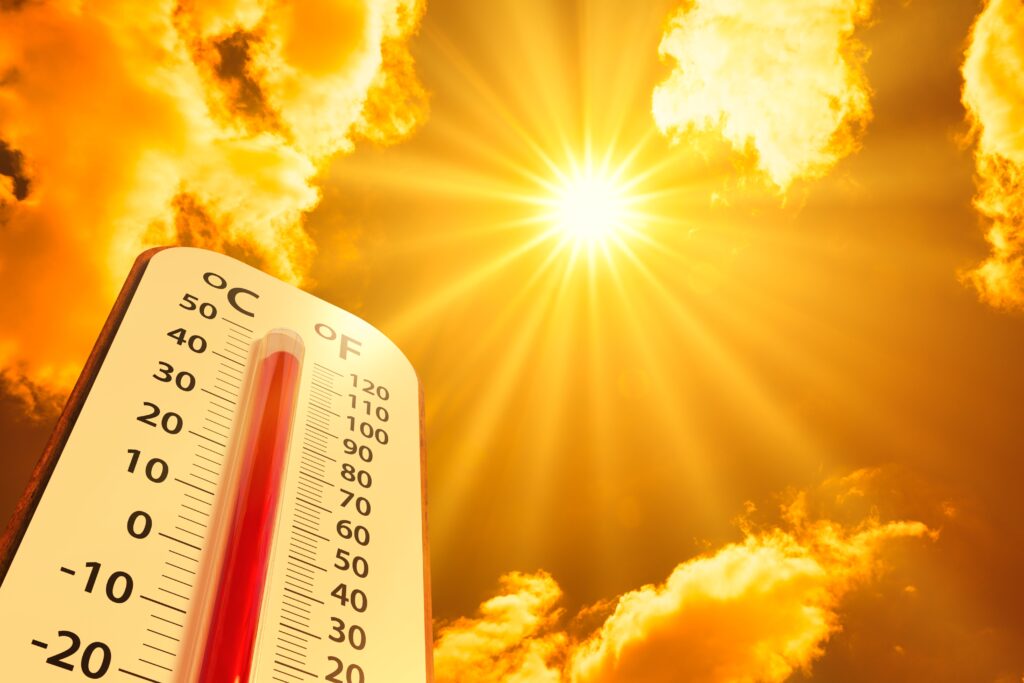今、世界中でCO2削減の取り組みが盛んです。
環境問題を目にしても必ず出てくる「CO2削減」の言葉ですが、一体なぜCO2削減が必要だと言われているのでしょうか?
企業ではどういう取り組みが行われているのか、個人でできるCO2削減対策が気になります…
今回はCO2削減はなぜ必要なのか、さらに、企業の取り組み事例から個人でできることをご紹介していきます。
CO2の削減はなぜ必要なの?

まずはじめに、CO2削減はなぜ必要なのか、わかりやすく解説していきましょう!
CO2削減は世界中が共通で取り組むべき事柄です。
その理由は、地球温暖化にあります。
CO2やメタンガスなどの温室効果ガスと呼ばれるものは、地球の温度を暖める働きがあります。
もし温室効果ガスが地球に存在しなかったら、地球の温度はマイナス19度くらいになると言われています。
しかし、逆にこの温室効果ガスが増えすぎると、気温が上昇し、温暖化してしまうのです。
実際に、世界の平均気温は上昇傾向にあり、近年はその気温上昇スピードが早まり、このまま進めば2100年までに1.1〜6.4度上昇すると言われています。
温暖化することで、海面の上昇や自然災害の増加、生物の減少など、地球上の全ての生き物に悪影響が及びます。
CO2は温室効果ガスの中でも特に、地球温暖化への影響が大きいと言われており、CO2削減の必要性が訴えられているのです。
CO2削減目標は?

では、具体的に、どのくらい削減したらいいのでしょうか?
じつは、環境省により2021年4月に、CO2などの温室効果ガスに関して具体的な目標値が定められています。
それは2030年度までに、46%削減(2013年と比較して)することです。
さらに、50%削減の挑戦を続けることも表明しています。
また、アメリカの削減目標は2005年と比較して50〜52%、ヨーロッパ連合は1990年と比較して55%、イギリスは1990年と比較して68%です。
日本を含めた上記の国全てで、2050年にはカーボンニュートラル実現を目標としています。
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出をゼロとすることを言います。
この削減目標は、年々強化されているため、次の見直しの際はもっと削減数が大きくなっている可能性があります。
そのくらい、CO2などの温室効果ガス削減は地球にとって大切な事柄なのです。
CO2削減のための企業の取り組みとは?

ここまでで、CO2削減の必要性や各国が目標値を掲げ行動していることがわかってもらえたと思います。
では、CO2削減のため、企業はどのような取り組みを行っているのでしょうか?
ここからは、企業のCO2削減の取り組み事例をご紹介しましょう!
1つ目は、運送業者の取り組みです。
運送業に欠かせない自動車は、CO2排出量のうちとても大きな割合をしめています。
そのことを受けて、ヤマトホールディングスと佐川急便は車両にハイブリット車や電気自動車のようなクリーンエネルギー車を採用し、近隣の配達では自転車の使用も積極的に行うことで、CO2削減に貢献しています。
2つ目は、イオンの取り組みです。
イオンは全国17000店舗以上、世界11カ国に進出する大型小売業です。
その全店舗で、2025年までに使用電力を100%再生可能エネルギーに切り替えることを目標にした取り組みが行われています。
その他にも、一般家庭から余剰電力の買取、地域への植樹など、サステナブルな活動に積極的に取り組んでいます。
3つ目は、トヨタ自動車の取り組みです。
車を作る工場をスリム化しただけでなく、使う電力を再生可能エネルギーに変更し、さらには今後工場から出るCO2をゼロにするという目標を掲げています。
トヨタ自動車のこれらの取り組みは大変高い評価を得ており、ブランド総合研究が行った調査では3年連続で最高評価を得ています。
4つ目は、サントリーの取り組みです。
サントリーと言えば、清涼飲料水ですが、そこで使用されるペットボトルのリサイクル技術を向上させ、なんと石油由来原料に比べCO2を約70%削減できるシステムの開発に成功しました。
また、2050年までにCO2排出量ゼロを目標としています。
5つ目は、ユニクロの取り組みです。
ユニクロは、店舗とオフィスの使用電力を100%再生可能エネルギーへ転換し、商品製造におけるCO2排出量も2019年から20%削減するという目標を掲げています。
どの企業も多くの人が知る有名企業ですね。
CO2削減の動きが、大企業から中小企業へと伝わっていくことが大切です。
CO2削減のために個人ができることは?

では、私たち個人がCO2削減のために、何かできることはないのでしょうか?
最後に、CO2削減のために個人ができることをご紹介して終わりたいと思います。
個人でできることの1つ目は、エアコンの温度設定です。
地球温暖化のため、夏の暑さがエアコンなしでは乗り切れない温度になってきました。
しかし、エアコンは家電の中でも多くの電力を使用する機器の1つです。
そのため、温度設定で少しでも電気の節約が必要になります。
例えば、冷房の際に1度温度を上げる、暖房の際に1度温度を下げるなどです。
冷房を1度上げると約13%、暖房を1度下げると約10%、電気代が節約できます。
それと比例してCO2の量も減らすことができ、一石二鳥です。
2つ目の個人でできることは、自動車の使用を控えることです。
経済産業省によると、1世帯あたりの平均CO2排出量は約3,900キログラムと言われており、その中でもガソリン車によるCO2排出量は全体の21.6%と2番目に多い割合でした。
(1番目は自宅にある全ての家電製品で47.6%)
そこを、半分ほど自転車や徒歩に置き換えると、世帯内で10%のCO2削減に繋げることができます。
3つ目の個人でできることは、待機電力のカットです。
使われていない家電であっても、コンセントにささっているだけで待機電力というのが発生します。
長時間使用しない場合は、コンセントを抜き、待機電力をカットしましょう。
そのことで、1世帯あたり年間6000〜7000円の節約、消費電力は5.1%の削減になります。
これが最も簡単にできるCO2削減方法ですね!
ちょっとした工夫で、個人でも地球のために活動することができるのです!!
まとめ
今回はCO2削減はなぜ必要なのか、さらに、企業の取り組み事例から個人でできることをご紹介しました。
CO2が排出されることで、地球温暖化に大きな悪影響を与えます。
それを受けて、世界各国でCO2削減の目標が掲げられました。
そして、企業もさまざまな方法で、CO2削減を目指した取り組みを行っています。
企業だけでなく、個人での対策もとっても大切です。
1人1人が地球のことを考え、ちょっとした工夫でCO2削減ができたらいいですね!
この記事を参考に一緒に取り組んでいきましょう!