
世間では、プラスチックが及ぼす環境問題が多く語られていますよね。
その一方で、地球に優しい「生分解性プラスチック」の開発が進んでいます。
今回は生分解性プラスチックについてわかりやすく解説!メリットやデメリットも合わせてご紹介していきます。
生分解性プラスチックとは?原料や種類は?

では早速、生分解性プラスチックについて、原料や種類なども詳しくご紹介していきましょう!
生分解性プラスチックとは
生分解性プラスチックとは、一定の条件が揃うことで、微生物の働きによって二酸化炭素と水に分解されるプラスチック製品のことを言います。
分解される場所は、例えば、土壌中や海中、コンポストの中など、微生物が活動しやすい場所があげられます。
一般的なプラスチックはそのような場所でも形を変えず残り続けるため、環境汚染などの原因となっています。
その点、生分解性プラスチックは分解され、自然に還るため、地球に優しいプラスチック製品であることがわかります。
ちなみに、生分解性プラスチックは「バイオプラスチック」の一種です。
バイオプラスチックは生分解性プラスチックとバイオマスプラスチックの両方のことを指します。
バイオプラスチックという大枠に、生分解性プラスチックと、また別の地球に優しいプラスチック「バイオマスプラスチック」が入っているというイメージですね。
今回は生分解性プラスチックがテーマですが、バイオマスプラスチックについても他の記事でご紹介しているので、ぜひそちらもご覧ください!
生分解性プラスチックの原料

さて、そんな地球に優しいプラスチックである生分解性プラスチックの原料は何なのでしょうか?
生分解性プラスチックの原料はいくつかあります。
1つ目は、トウモロコシやサトウキビなどの植物です。
2つ目は、石油や石炭などの化石燃料です。
3つ目は、上記の2つを混合した原料です。
石油といえば、一般的なプラスチックの原料でもありますよね。
生分解性プラスチックは原料にこれを使わなければならないというルールはありません。
最終的に、二酸化炭素と水に分解することができれば、生分解性プラスチックと呼ぶことができます。
ただ、原料の違いによって種類分けされ、その呼び名も変わります。
生分解性プラスチックの種類
ここからは、生分解性プラスチックの種類をご紹介しましょう!
まず、トウモロコシやサトウキビなどの植物からできた生分解性プラスチックの代表的な名前を紹介します。
植物由来の生分解性プラスチックは、ポリ乳酸(PLA)、ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)などです。
低耐熱性や透明性の高さ、コンポスト中での分解が得意という特徴があり、冷凍食品の包装材やレジ袋、農業フィルムなどに使用されています。
お次は化石燃料を原料とした生分解性プラスチックの種類です。
化学燃料を原料とした生分解性プラスチックには、ポリビニルアルコール(PVA)、ポリグリコール酸(PGA)などがあります。
PVAは造膜性、透明性、高強度、ガスバリア性、防曇性、非帯電性などに優れていることからテレビやパソコンモニターの偏光フィルターに、PGAは酸素ガスや炭酸ガスを透過させにくいという特徴から炭酸飲料やビール、薬品、液体調味料などの容器に使用されています。
そして、植物と化石燃料を混合して作られた生分解性プラスチックには、ポリブチレンサクシネート(PBS)、澱粉ポリエステル樹脂などがあげられ、農業フィルムから使い捨て容器などの幅広い用途で使用されています。
生分解性プラスチックと一括りにいっても、その中でいろんな原料が使われ、いろんな種類のプラスチックが作られているんですね。
生分解性プラスチックのメリットは?

そんな生分解性プラスチックには、どんなメリットがあるんでしょうか?
前述の解説と少し重複しますが、わかりやすく整理していきましょう。
メリット① 分解される
1つ目は、二酸化炭素と水に分解される点です。
生分解性プラスチックの1番の特徴で、メリットですよね!
プラスチックのゴミや環境汚染問題は深刻なので、分解されることでこれらの問題を解決に近づけることができます。
メリット② CO2排出量が少ない
2つ目は、たとえ燃焼処理されたとしてもCO2排出量は少なくて済む点です。
例えば、生分解性プラスチックであるポリ乳酸の袋と、一般的なプラスチックであるポリエチレンの袋を燃やした時、ポリエチレンの袋のほうが熱量や二酸化炭素の量が2倍多く出たという実験結果もあります。
以上のメリットを見ると、やはり生分解性プラスチックは地球に優しいプラスチックであることがわかりますね〜
生分解性プラスチックのデメリットは?
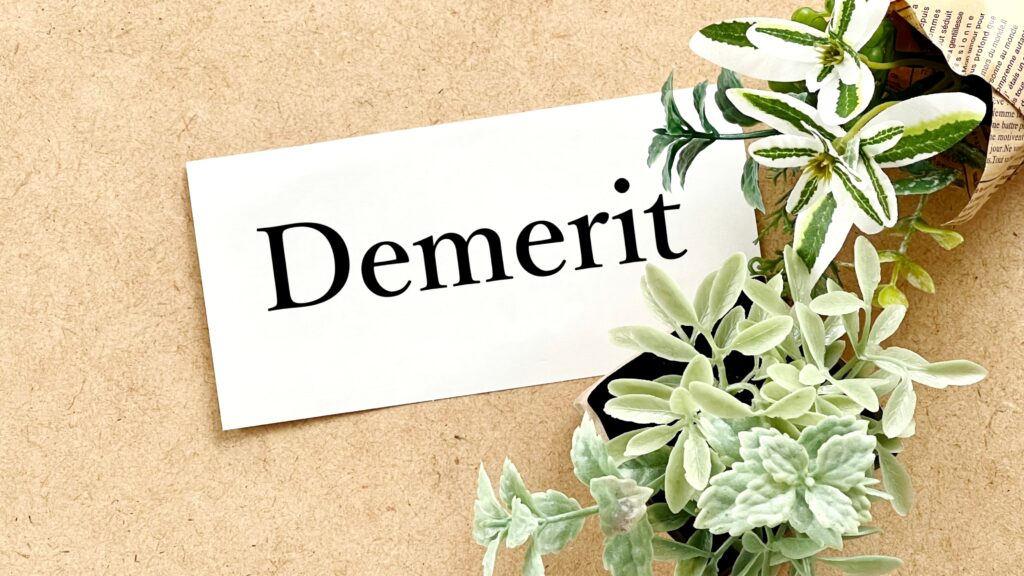
一方で、生分解性プラスチックにはデメリットも存在します。
デメリット① コストが高い
1つ目は、コストが高いことです。
まだ製造数が少ないため、作るのにコストがかかってしまい、販売価格も一般的なプラスチックより高くなってしまいます。
デメリット② 分解できる環境が限られる
2つ目は、分解できる環境が限られることです。
生分解性プラスチックは土壌中や海中、コンポストの中などで分解されるとご紹介しましたが、種類によっては土壌中では時間がかかるもの、海中では分解しないものもあります。
生分解性プラスチックだからといって、どこでも二酸化炭素と水に戻ってくれる訳ではないのです。
また、分解スピードも環境によって違うため、安定しないというデメリットがあります。
デメリット③ 分解させないと特徴が生かせない
3つ目は、分解させないと特徴が生かせないことです。
今や生分解性プラスチックを知る人も増えてきましたが、まだ認知度が高いとは言えません。
何も知らずに通常のプラスチック同様に廃棄してしまえば、生分解性の特徴を生かすことができず製造までのエネルギーやコストが無駄になってしまいます。
以上のデメリットは、全て生分解性プラスチックが今以上に普及し、製造工場や分解する処理工場が整い、消費者の認知度が上がれば解決できる問題ですね!
今後の普及を期待して待ちましょう!
まとめ
今回は生分解性プラスチックについてわかりやすく解説!メリットやデメリットも合わせてご紹介しました。
生分解性プラスチックは一定条件が揃うことで、二酸化炭素と水に分解されるプラスチックのことを言います。
メリットは地球に優しいところ、デメリットは普及が少なく設備や認知度が低いために考えられる点ばかりでした。
これから、生分解性プラスチックなど、地球に優しい製品の開発がより進むことで、プラスチック問題の解決に近づくことを願っています!


