
2023年11月7日、東京都で気温27.5度が観測され、100年ぶりに11月の最高気温を更新しました。
その他、日本各地で25度以上の夏日を記録。
今年の冬はいつくるんだろうと思った人も多いでしょう。
案の定、2023年から24年にかけて、暖冬の予想とのこと!!
今回は、2023〜24年は暖冬?気温の予想やその影響、メリット・デメリットに加え、過去の暖冬はどうだったのかもご紹介します。
2023年の冬は暖冬なの?その影響とは?

まずは、2023年の冬は暖冬なのか、これまでの気温と今後の気温の見込みをご紹介しましょう。
① これまでの気温と今後の見込み
皆さん実感があると思いますが、今年の日本の夏(6〜8月)は平均気温が例年より1.76度も上回り、統計開始から125年の間で最も高い気温が記録されました。
9月、10月と異例の暑さは続き、11月でさえも東京都を中心に夏日が3日間続く異常な事態となっています。
また、11月から来年1月までを対象とした気象庁の3ヶ月予報では、12月の北海道・東北を除いた全ての月、地域で「平年並みか高い」もしくは「高い」気温となる見込みと発表。
つまり、2023年〜24年の冬は全国的に暖冬であることを示唆しました。
② 暖冬になる理由は「エルニーニョ現象」と「温暖化」
では、一体どうして今年の冬は暖冬になるのでしょうか?
その大きな理由は、エルニーニョ現象です。
エルニーニョ現象とは、ペルー沖の海面水温が基準値よりも0.5度以上高い状況が1年ほど続く現象を言い、世界各地に干ばつなどを引き起こし、水不足などの深刻な被害をもたらします。
エルニーニョ現象が発生している際は、日本が、特に西日本が暖冬傾向になると言われています。
しかも、今年はこのエルニーニョ現象のさらに上をいく、スーパーエルニーニョになる可能性も指摘されています。
スーパーエルニーニョとは、海面水温が1.5〜2度高い状況のこと。
そのため、より一層、暖かい冬がやってくる可能性が高くなるのです。
また、温暖化などで、地球の大気全体の温度が高くなっていることも、全体的に気温が高まることに影響しています。
③ 日本海側は雪が少ないが突然の大雪にも注意
暖冬であれば、今年の冬は雪が少ないだろうと考える人も多いでしょう。
日本海側に関しては、雪が少ない予報が出ています。
しかし、太平洋側では日本列島の南岸を東へ進む「南岸低気圧」によって寒さが引き込まれ、その寒さが居座ることで突然の大雪となる可能性があります。
予想しにくい低気圧なので、こまめに天気予報を確認することがおすすめです。
暖冬のメリット・デメリットは?
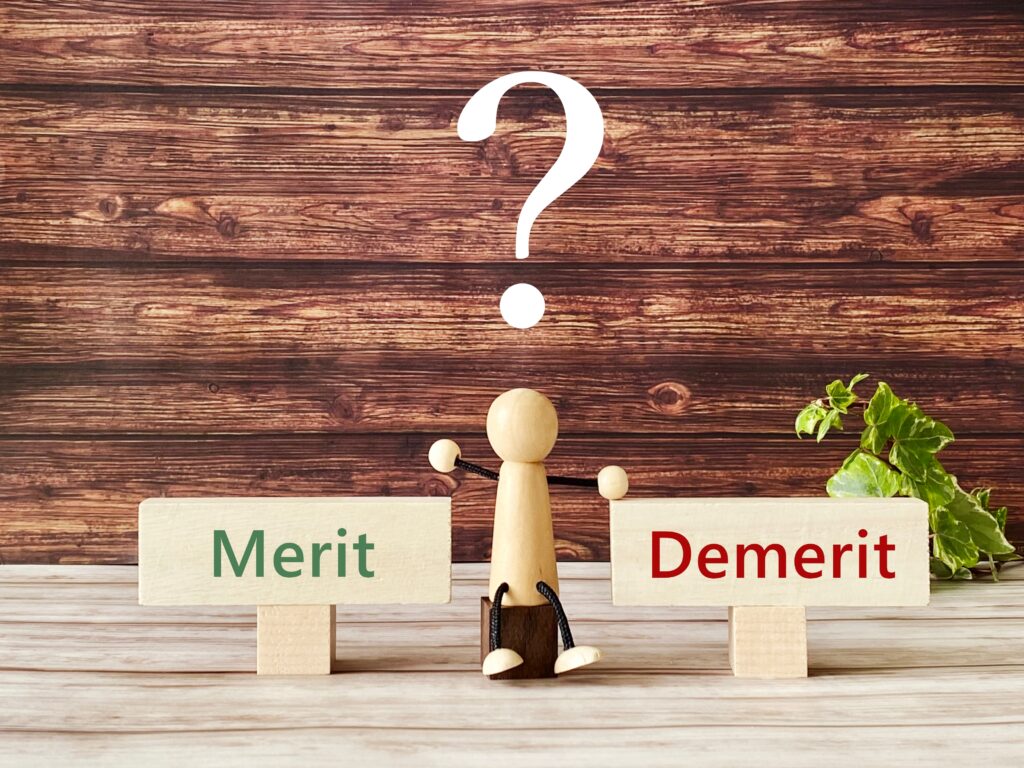
ここまでの説明で、今年の冬は暖冬で、その理由などもわかってもらえたと思います。
夏の暑さは身体にこたえますが、冬の暖かさはちょっと有難いかも??
そう感じる人も多いでしょう。
では、ここからは暖冬のメリット・デメリットについてご紹介していきます。
暖かくても良いことばかりではありませんよ!
① 暖冬によるメリットは何?
まずは、暖冬によるメリットをご紹介します。
1つ目は冬の光熱費が安く済むことです。
暖房は冷房以上に電気代がかかりますし、電気代高騰で家計が心配な方も少なくないはず。
しかし、暖冬だと暖房を使うシーンが減り、光熱費を抑えることができます!
2つ目のメリットは、野菜の値段が下がりやすくなることです。
暖冬だと、トマトや白菜、ホウレンソウなどの野菜の生育がよくなり、収穫量も増えます。
そのため、例年の2割程度、価格が安くなると言われているのです。
光熱費の節約、野菜の値下げと、私たち個人にとっては暖冬はかなりメリットが高いように思えますね。
② 暖冬によるデメリットは何?
しかし、暖冬は良いことばかりではなく、むしろデメリットのほうが深刻だと考えられています。
暖冬によるデメリット1つ目は、スキー観光業界の大打撃です。
冬が暖かいと雪が降りにくく、例え降ったとしてもすぐに溶けてしまいます。
つまり、スキーシーズンは短縮され、そこで働く人々の仕事を奪ってしまうのです。
スキーだけではありません。
暖冬で、暖房器具の売れ行きは落ち込み、鍋や冬物衣類などの冬向け商品も売れにくくなります。
つまり、暖冬は日本の景気にも悪影響を与えるということです。
また、環境面でのデメリットも考えられます。
通常は氷点下を下回るような冬に多くの昆虫が死滅します。
しかし、暖冬では昆虫が冬を生き延び、繁殖が早まり、量も増えてしまいます。
昆虫はよい昆虫ばかりではなく、人間にとっては害になる昆虫もたくさんいます。
農作物が害虫にやられれば、冬の間は野菜が安くなっても夏の野菜はどうなるかわかりません。
その他にも、雪が降らないことでの水不足、花の開花が早まることで受粉を担当する虫が来ず植物の育ちが悪くなるなど、いろんな可能性が考えられます。
メリットはとても単純なものが多かったですが、デメリットは経済から地球環境のことと複雑で幅広い点が多いことがわかりますね。
暖冬だからと言って、手放しで喜ぶことはできないでしょう。
過去の暖冬はいつ?気温は?

さて、そんな暖冬が今年に迫っているのですが、最後にこれまでの暖冬はどんな感じだったのか、気温なども合わせてご紹介していきたいと思います。
最近の暖冬だった年は、2006年〜07年、2015年〜16年、2018年〜19年、2019年〜20年です。
2006年から2015年は9年も間があるにも関わらず、それ以降は暖冬となる年の間隔が狭まっていることがわかります。
この中で特に暖かかった年は2019年〜2020年の冬です。
東・西日本の気温は統計開始後の122年間で最も高く、積雪量もかなり少ない状態でした。
そのため、スキー場の悲痛の声が報じられたり、暖かさ故に桜の開花が早まったり、混乱の多い年となりました。
ちなみに、この時の気温は平年に比べ、東日本でプラス2.2度、西日本でプラス2度だったと言われています。
まとめ
今回は、2023〜24年は暖冬?気温の予想やその影響、メリット・デメリットに加え、過去の暖冬はどうだったのかをご紹介しました。
今年の冬は暖冬で、日本各地で暖かくなると予想されています。
暖冬はエルニーニョ現象によってもたらされますが、スーパーエルニーニョの影響でさらに暖かくなる可能性が高いです。
光熱費が抑えられ、野菜が安くなるのは有難いメリットですが、それ以上に深刻な経済的・環境面でもデメリットが多いことがわかりました。
直近の暖冬である2020年には記録的気温となりましたが、今年もその記録を更新してしまわないか心配ですね。
こまめに天気予報をチェックしながら、今年の冬を乗り切っていきましょう。


